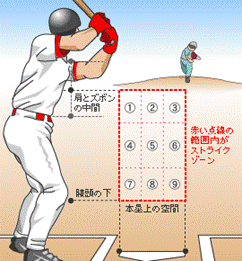毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!
メールマガジン配信登録は☆こちらから☆
趣味と仕事
MLB野球観戦の仕方、そして「野村ノート」に学ぶこと
JR東日本メカトロニクス株式会社
小田島 裕之
小学校3年のリトルリーグから大学生まで野球をしていました。引退後は会社の野球好きなメンバーと草野球を楽しむ日々を10数年前までしていましたが、体がついてこず……。今はTVで「MLB(メジャーリーグ・ベースボール)」を観戦する日々を送っています。日本人選手が大活躍するMLBについて、元ピッチャーでもある私のTV観戦の仕方を少し紹介します。
「野村ノート」からの、カウントで投げる球種
私の高校時代では残念ながら「野村ノート」(筆者は野村克也、以下ノムさん)を読むことはできませんでした。私が草野球で楽しんでいる2005年に発売されたこの本は、ノムさんのいう「データ野球」から生まれた、皆さんが野球をTVでご覧になるセンターから移された画面(ピッチャー、キャッチャー、バッター、そして審判)で繰り広げられる駆け引きをそれぞれの立場で解説した本になると思います。
私の時代は、140km以上をなげるピッチャーはあまりいなく、球種もストレートとカーブが基本でした。バッターにおいては、素振りの回数、日ごろからのバッティング練習、練習試合の総合的な結果からレギュラーになる感じで、少なくても他の選手より「優れている」という判断によってレギュラーを勝ち取っていたような気がします(中には両親が頑張ってレギュラーをつかむ方もいましたが……)。
ピッチングにおいては、外角・内角を交互に投げるのを基本に、高低差・ストレートと変化球の緩急にて仕留める、ホームベース上のストライクゾーン内での勝負が多かったような気がします。このような時代ですから野村ノートを読んだときは、データ野球の意味、ピッチャー心理、バッター心理が少なからぬ驚きとともに「野球の楽しさ」を感じた瞬間でした。
少しこの本の内容を紹介しますと、
①打者の決めつけを利用する: カウント3(ボール)-2(ストライク)では、打者は「ストライクが来る」と決めつけがち。その裏をかき、あえてボールゾーンへ誘い球を投げ、選球眼を狂わす。
②追い込んだ後(2ストライク): 追い込まれた打者は、ストライクを取りに来る球を待っている。そこで、ボールゾーンへ少し外れる変化球を投げ、手を出させて凡打に打ち取る。
③打者有利なカウント(2ボール): 2ボールなど投手不利なカウントでは、安易にストライクを取りに行くと痛打される危険があり、打者が狙っていない球種やコースを選択し、一度仕切り直すための配球を考える。
※これはバッターの蓄積されたデータにより決めることが多い
プロ野球の試合観戦中にバッターへの危険なボール(デッドボールになりそうなボール)が稀にありますが、あれも手がくるったのではなく、心理を利用した次に投げるボールのために投げた1球(仕留めたい1球)が多いです。
参考図:sports-rule.com
現在の野球は、当時から比べると試合内容、各選手のレベルなど全てにおいて優れています。監督・コーチの指導も具体性があり、我々の時代は「ブーンっと、バーンっと振ってみろ!」など技術を感じられない状況でした。選手自ら考えて自分の底上げをする努力は変わりませんが、根拠となるレベルアップは現在とはかけ離れていたと思います。
さて、プレーヤーを退き、TV観戦に趣味をかえて野球にかかわってきましたが、特にMLBは最近、楽しく観戦させてもらっています。本塁打を量産する、平均40cmも移動する変化球や160km超すストレートと次元が違います!
しかも今述べたことを日本人がしていること自体が想像を超えています。世間的には漫画のようだと言われています。活躍する日本人が増えてメディアでたくさん目にすることが多くなり、各チームで活躍している選手を反面羨ましく思いながら観戦させてもらっています。
「野村ノート」で学ぶ社会人と組織
野村ノートは、その経験から仕事に置き換えると様々な教訓が得られました。ノムさんの有名な言葉に「金を残すは三流、仕事を残すは二流、人を残すは一流」があります。解釈は人それぞれですが、みなさんの会社ではどうでしょうか?
一流(人)を残す:部下や後輩を育成し、彼らがその後も活躍できるような能力や精神を育むことが真の成功であるという考え。
二流(仕事)を残す:自分だけが成果を出すのではなく、組織やチームがその成果を継続的に発展させられるような仕組みやノウハウを残す。
三流(金)を残す:短期的な利益や目先の金銭的成功に固執するのではなく、長期的な視点で組織や人の成長を目指すことが重要である。
会社での立ち位置(役職や担当)で見方は変わりますが、この流儀はあくまでも結果であり通常はその結果が出るように汗をかいているのが現実ではないでしょうか?
そんな努力している人にノムさんはこのように励ましています。「努力に即効性はないけれど、努力は人を裏切らない」。
地道な努力の重要性:すぐに結果が出なくても、継続的な努力は必ず将来の糧となり、信頼や成果に繋がることを信じ、日々の業務に取り組む。
人材育成への応用:部下の成長には時間がかかることを理解し、焦らず、着実に能力を引き出すように教育やサポートを行う。
ここまでくると少し「昭和感」が出ているような気がしますが、私の場合、今でも基本は、部下である方が上司(先輩)の背中を追い続ける心理的な情景は、上司の努力であり、人材育成がそこそこうまくいっている成果ではないかと思っています。現在も上司を敬い、背中を追う環境で仕事ができていると感じています。
しかしその反面、コミュニケーションや会話に工夫を行い質問力を高め、人と人の距離感を保ち、必要以上に会話をしないような現在の社会現象には、仕事を好きになり、人や交流を好きになり、といった鎖のない時代とはだいぶかけ離れた状況になっていると感じています。少し人間臭い環境が私にあっていると思いますが、皆さんはどうでしょうか?
■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら